EDEI(就労継続支援A型)は、障がいをお持ちの方が安心して働きながら、自分らしさを発揮できる場所を目指しています。就労支援を通じて、一人ひとりの特性や体調に寄り添い、無理のないペースでスキルを身につけられるよう取り組んでいます。日々の業務を通じて、自信を持って新しいことに挑戦し、着実に成長していただけるよう、安心して働ける職場づくりを心掛けています。「自分らしく働きたい」「就労支援について詳しく知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。働き方を一緒に考え、全力でサポートいたします。
2025年07月20日
就労支援を登録する手順と必要書類まとめ!A型B型移行支援にも対応
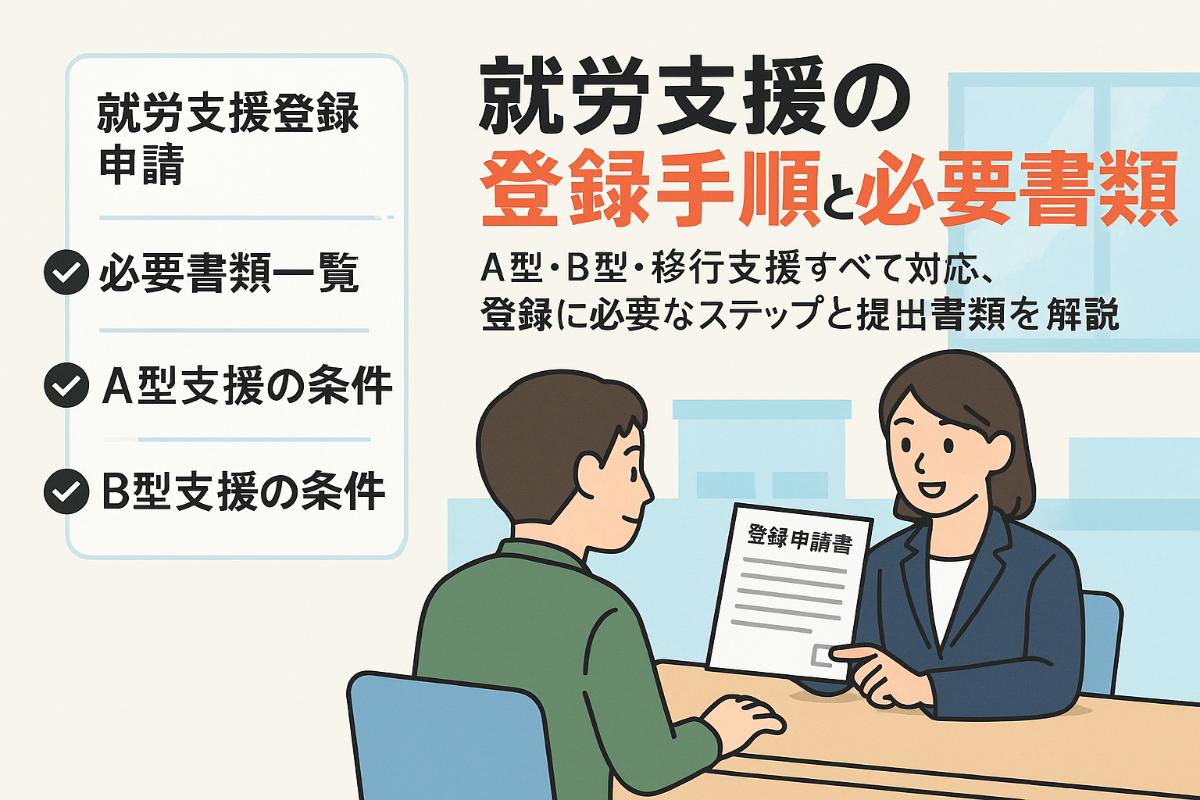
就労支援の登録を考えているけれど「何から始めればいいのか分からない」「申請の手続きが複雑そうで不安」と感じてはいませんか。
実は、就労支援サービスをスムーズに利用するためには、障害者手帳の有無、診断書、サービス等利用計画など、自治体や厚生労働省が定めた基準を正しく理解することが大切です。とくに現在、就労継続支援A型やB型、就労移行支援などの制度は全国に広がっており、登録方法や受給者証の発行までの流れにも地域差があります。
また、登録支援機関や相談支援事業所との連携を怠ると、受給者証の交付が遅れたり、希望する施設に通所できないなどの支障をきたす可能性もあります。就労移行支援事業所やB型施設の見学、体験、面談などを効率よく進めるためには、正確な情報収集と書類準備が欠かせません。
最後まで読めば、申請でつまずかないための実践的な準備が整い、あなたに合った支援制度の選び方も見えてくるはずです。

| EDEI(就労継続支援A型) | |
|---|---|
| 住所 | 〒471-0034愛知県豊田市小坂本町4丁目6-7 エクセレント2014 1階 |
| 電話 | 0565-41-7505 |
就労支援とは何か?制度の種類と対象者の基礎知識
就労支援の種類別解説(A型・B型・移行支援・選択支援)
就労支援とは、障害や難病などにより一般企業での就労が困難な方に対して、就労の機会やスキル習得、就職支援などを提供する福祉サービスの総称です。制度は主に福祉型の支援で、厚生労働省の管轄のもと、障害者総合支援法に基づいて運営されています。
現在、日本国内には複数の就労支援制度が存在しており、それぞれ対象者や目的が異なります。以下に主な支援制度をまとめました。
| 支援の種類 | 対象者 | 雇用契約の有無 | 工賃・給与 | 主な目的 | 特徴 |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約を結ぶことが可能な障害者 | あり | 最低賃金以上 | 一般就労に向けた実務訓練 | 企業に近い形での業務提供。労働法の適用あり |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約が困難な障害者 | なし | 工賃制 | 働く習慣の獲得と生活リズムの安定 | 身体的・精神的負担が軽く、柔軟に働ける |
| 就労移行支援 | 一般企業への就職を目指す方 | なし | なし(訓練提供) | 就職に必要なスキルと知識の習得 | 利用期間は原則2年。企業見学や面接支援あり |
| 就労選択支援 | 就労系サービス選定が必要な障害者 | なし | なし | 自身に適した制度の選定と導入支援 | 新設制度。選択支援員の支援によりマッチング支援を実施 |
就労継続支援A型は、障害を抱えながらも労働能力があり、雇用契約を結べる方に向けた制度です。労働法に基づいた最低賃金が保証されるため、収入の安定性が高いのが特徴です。ただし、事業所側にとっては「就労支援施設 開業 資格」や「管理者 要件 厚生労働省」の条件を満たす必要があり、一定の設備や職員配置が求められます。
一方、就労継続支援B型は、比較的体調の波がある方や支援を多く必要とする方に適しています。雇用契約は結ばれず、工賃という形で報酬が支払われます。働くことで生活のリズムを整えたり、社会とのつながりを持つことが目的とされており、事業所側もビジネスモデルの多様化が進んでいます。
誰が対象になる?障害者手帳・特定疾病・難病の対象範囲
就労支援制度を利用するためには、「誰が利用対象となるのか」を正確に理解する必要があります。一般的に、就労支援の対象者は障害者手帳を所持している方や、特定の診断名がある方です。ただし、制度ごとに要件は異なるため注意が必要です。
以下は、支援制度を利用するうえでの対象要件の主な分類です。
| 区分 | 対象の種類 | 認定手段 | 主な必要書類 |
| 身体障害者 | 身体機能に障害がある方 | 身体障害者手帳(1級〜6級) | 医師の診断書、障害者手帳の写し |
| 知的障害者 | 知的能力に制限がある方 | 療育手帳(A1~B2など) | 判定機関の評価結果 |
| 精神障害者 | 統合失調症、うつ病、双極性障害など | 精神障害者保健福祉手帳 | 医師の診断書、手帳コピー |
| 難病患者 | 指定難病を抱える方 | 診断名・指定病名による | 特定医療費(指定難病)受給者証 |
| 発達障害 | 自閉スペクトラム症、ADHDなど | 手帳がない場合も可 | 医師の診断書、福祉窓口での確認書類 |
また、障害者手帳がない場合でも、医師の意見書や診断書によって就労支援の対象になるケースもあります。たとえば、「就労移行支援 手帳なし」という検索がされるように、手帳を持たずとも医師が支援の必要性を認めれば自治体判断でサービス利用が認められることがあります。
特に就労移行支援では、サービス利用開始時にアセスメント(生活状況・就労意欲・スキルなどを調査するプロセス)を実施し、本人が一般企業への就職を現実的に目指せる状態かを評価します。このアセスメント結果に基づいて、サービス等利用計画を作成し、自治体へ提出します。
就労支援に登録する流れと必要書類!
申請前の準備!アセスメント・障害者手帳の確認・相談支援
就労支援サービスを利用するには、事前の準備が非常に重要です。準備段階を怠ると申請の遅れや利用対象外となる可能性もあるため、丁寧に段階を踏む必要があります。ここでは、支援開始前に必要なアセスメントの受講、障害者手帳の有無確認、相談支援事業所との連携について解説いたします。
最初に必要なのは、本人の就労希望や生活状況、障害特性などを客観的に把握する「アセスメント(評価)」です。これは福祉サービス等の提供に必要な情報を整理し、個別支援計画の基礎資料として用いられます。多くの市区町村では、「相談支援専門員」と呼ばれる有資格者が面談を通じてアセスメントを行い、その結果をもとに計画相談支援を策定します。この計画は就労継続支援A型・B型、就労移行支援、さらには就労定着支援に至るまで、すべてのサービスで必要とされるため、最初の重要ステップといえます。
次に確認すべきなのが、障害者手帳の有無です。精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳のいずれかが支援の対象資格となりますが、手帳を持っていない方でも、医師の診断書や意見書によって支援対象となる場合があります。特に、難病や発達障害、知的障害といった一部の特定疾病が指定難病と認められているケースでは、手帳がなくても医師の所見で利用が認定される場合があります。この判断基準は各自治体の福祉課や障害福祉担当窓口で異なるため、事前に確認が必要です。
加えて、相談支援事業所との連携も不可欠です。相談支援専門員はアセスメントから計画書の作成まで、本人に寄り添いながら手続きをサポートします。障害特性に応じたアドバイスや、どのサービスが適しているかといった情報も提供してくれるため、安心して支援開始の第一歩を踏み出すことができます。
また、以下のような準備チェックリストを活用すると効率的です。
| 項目 | 内容 | 備考 |
| アセスメント面談 | 相談支援専門員と面談、支援計画案の作成 | 予約が必要 |
| 障害者手帳の確認 | 身体・知的・精神のいずれかを所持、または診断書を取得 | 医師の所見が必要な場合もある |
| 医師の診断書 | 手帳がない場合は必須 | 診断名や症状の記載が必要 |
| 利用希望施設の情報収集 | 就労継続支援A型・B型、移行支援など | 見学や体験利用が望ましい |
| 家族や支援者との相談 | 生活面や通所面のサポート体制を確認 | 支援体制の確認が必要 |
これらの初期準備を丁寧に行うことで、後の申請手続きがスムーズになり、受給者証の交付までの期間も短縮されやすくなります。特に就労支援の現場では、準備不足による二度手間や申請ミスがよく見られるため、事前確認の徹底が大切です。
必要書類一覧と記入方法(申請書・診断書・計画書)
就労支援を受ける際には、多数の書類を提出する必要があります。これらの書類は、利用者の状況や希望、障害の状態を自治体に正確に伝えるための重要な資料です。以下に、基本的な必要書類とその記入方法について詳しくご説明いたします。
自治体や施設によって微細な違いはありますが、共通して求められる書類は主に以下の通りです。
| 書類名 | 内容 | 提出先 |
| 申請書類 | 支援の種類、希望する施設、基本情報の記載 | 市区町村福祉課 |
| 医師の診断書または意見書 | 障害の種類や程度、日常生活・就労への影響を記載 | 市区町村福祉課 |
| サービス等利用計画案 | 相談支援事業所が作成。本人の希望や支援目標を記載 | 市区町村または施設 |
| 障害者手帳の写し | 精神、知的、身体いずれかの障害者手帳のコピー | 市区町村福祉課 |
| 世帯状況届 | 同居家族や収入状況の確認。支給量の判断に影響 | 市区町村福祉課 |
| 同意書・個人情報提供書 | 各機関との情報共有の同意書 | 市区町村福祉課 |
申請書の記入では、誤字や不備があると差し戻されることも多く、特に希望するサービス区分(A型・B型・移行支援など)の選択は慎重に行う必要があります。また、「本人による記載」と「支援者による代筆」どちらも認められますが、本人の意思をきちんと反映することが求められます。
医師の診断書については、障害の種類に応じて様式が異なる場合があります。精神障害者であれば精神科医の意見書、知的障害の場合は療育手帳に基づいた意見書が必要になることもあります。提出時はコピーではなく、原本または原本確認済の写しが必要となるケースが多いため、事前に自治体へ確認しましょう。
事業所別!就労支援施設の選び方と登録フローの違い
就労支援A型/B型/移行支援の違いと選び方
就労支援施設には主に「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」の3種類があり、それぞれに対象者や支援内容、運営方法が異なります。適切な支援を受けるには、自身の状況や希望する就職スタイルに合った施設を選ぶことが重要です。
まず、就労継続支援A型は、雇用契約を結んで働きながら支援を受ける形態で、一定の労働能力がありながらも一般就労が困難な障害者を対象としています。事業所との雇用契約に基づき最低賃金以上の工賃が支払われ、福祉的支援と実務の両立が実現されます。
一方、就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに作業訓練を行う非雇用型の支援です。精神的・身体的な制約によりA型での勤務が困難な方が対象で、より柔軟な作業スケジュールや支援体制が特徴です。作業内容は軽作業や製造補助、パッケージング、農作業など多岐にわたりますが、工賃はA型よりも低めです。
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害者に対し、職業訓練や就活支援、職場定着支援などを提供する制度です。利用期間は原則2年間で、利用には医師の診断書や障害者手帳等の確認が必要となります。利用者は企業見学や職場実習、履歴書添削や面接練習といった支援を通じて、就職を目指していきます。
以下に主な違いをまとめます。
| 支援種別 | 対象者の主な状態 | 雇用契約 | 工賃水準 | 就職支援の有無 |
| A型就労継続支援 | 一般就労が困難だが就業可能 | あり | 最低賃金以上 | 一部あり |
| B型就労継続支援 | 就業が困難、体力や精神的負荷がある | なし | 数千円〜数万円 | ほぼなし |
| 就労移行支援 | 一般就労が可能と判断される | なし | なし | 充実(企業連携、定着支援等) |
ご自身が安定した労働環境を求める場合はA型、リハビリや日中活動を重視したい方はB型、一般企業への就職を目指す方は就労移行支援が適しています。地域や施設によって特色がありますので、体験見学や市区町村の福祉課での相談を通じて、最適な選択をしましょう。
登録支援機関や認定法人との関係と信頼性の見極め方
登録支援機関は、就労支援施設を立ち上げたり、利用希望者の相談窓口として機能する重要な存在です。特にA型・B型事業所の新設時や、利用者の申請時には、これらの支援機関や認定法人との連携が欠かせません。
信頼性を判断する際のチェックポイントは以下のとおりです。
- 自治体または厚労省の指定を受けているか
- 過去の実績・運営年数が明示されているか
- 提示される支援内容が具体的であるか
- 明朗な料金体系であるか(初期費用、書類作成費用など)
- 契約書や利用規約が明文化されているか
- クチコミや相談実績、認定法人からの推薦などの外部評価
また、悪質なケースとしては、「助成金だけを目的とした形だけの支援」「十分な支援体制のない委託型施設」「誤解を与える契約書」などが問題となることがあります。信頼できる機関を選ぶには、必ず第三者評価機関の情報、厚労省の公式公開情報、市区町村の福祉課からの紹介などを元に、事前に徹底的な調査が必要です。
以下に「登録支援機関選びの比較項目」を示します。
| 評価項目 | 確認内容 |
| 指定状況 | 厚生労働省または自治体による認定があるか |
| 実績・信頼度 | 実施年数・相談件数・継続率の開示 |
| 契約内容の透明性 | サービス範囲、費用、期間が明記されているか |
| 対応スタッフの質 | 専門資格(社会福祉士、精神保健福祉士等)の有無 |
| 事後フォロー体制 | 書類作成後の自治体対応、運営支援の有無など |
信頼性が担保された支援機関は、制度の理解や実務の進行をスムーズにし、事業所設立や利用希望者にとって安心できるパートナーとなります。
まとめ
就労支援の登録は、多くの情報と手続きを伴うため、不安や戸惑いを感じている方も多いかもしれません。「自分に合った支援制度はどれなのか」「必要書類は何を用意すればいいのか」と悩むのは自然なことです。しかし、正確な情報を得て、段階的に準備を進めることで、誰でも安心して支援を受けることが可能になります。
さらに、実際に支援を利用した方々の体験談や口コミを通じて、制度のメリットと課題も浮き彫りにしました。「就職につながった」「生活リズムが整った」といった前向きな声がある一方、「期待とのギャップを感じた」「支援が形骸化していた」といった現実的な意見も紹介しています。これにより、自分に合った事業所を見極めるヒントが得られたのではないでしょうか。
制度や手続きは年々変化しており、現時点では「就労選択支援」の導入など、さらに選択肢が広がりつつあります。迷ったときは、厚生労働省の公式資料や市区町村の福祉課、登録支援機関に直接相談することで、安心して次の一歩を踏み出せます。
EDEI(就労継続支援A型)は、障がいをお持ちの方が安心して働きながら、自分らしさを発揮できる場所を目指しています。就労支援を通じて、一人ひとりの特性や体調に寄り添い、無理のないペースでスキルを身につけられるよう取り組んでいます。日々の業務を通じて、自信を持って新しいことに挑戦し、着実に成長していただけるよう、安心して働ける職場づくりを心掛けています。「自分らしく働きたい」「就労支援について詳しく知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。働き方を一緒に考え、全力でサポートいたします。

| EDEI(就労継続支援A型) | |
|---|---|
| 住所 | 〒471-0034愛知県豊田市小坂本町4丁目6-7 エクセレント2014 1階 |
| 電話 | 0565-41-7505 |
よくある質問
Q. 就労支援を利用する場合、登録から受給者証交付までにかかる期間はどれくらいですか?
A. 就労支援 登録の流れは市区町村によって若干異なりますが、一般的にはアセスメント実施から受給者証の交付まで2週間〜1か月程度かかります。特に精神障害者保健福祉手帳を所持していない方の場合は、医師の診断書や相談支援事業所との面談などが必要になり、さらに7日〜14日程度の期間が追加でかかることもあります。申請の不備や記載漏れがあるとさらに遅延するため、事前の準備と必要書類の確認が重要です。
Q. 障害者手帳がない場合でも就労支援に登録できますか?
A. 障害者手帳がなくても、就労支援 登録は可能です。たとえば就労移行支援では、精神疾患や発達障害、特定疾病の診断がある場合、医師の意見書や診断書をもとに市区町村が福祉サービスの必要性を認めれば利用できます。実際、診断書のみで申請を進めたケースも多く、特に若年層のうつ病や軽度発達障害などで増加傾向にあります。判断基準は自治体により異なるため、相談支援事業所との連携がカギになります。
事業所概要
事業所名・・・EDEI(就労継続支援A型)
所在地・・・〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町4丁目6-7 エクセレント2014 1階
電話番号・・・0565-41-7505

